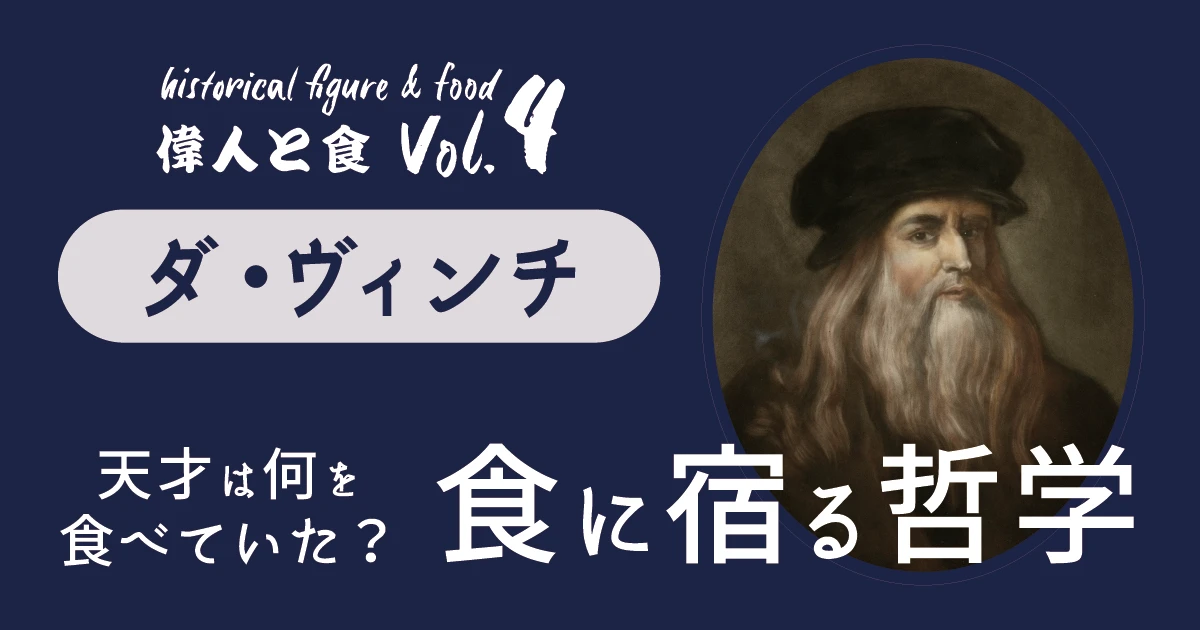
天才は何を食べていたのか?レオナルド・ダ・ヴィンチの食に宿る哲学
食のこと
「モナ・リザ」や「最後の晩餐」で知られるルネサンスの巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチ。
芸術、科学、建築、解剖学に至るまで、あらゆる分野に足跡を残した“万能の天才”です。
.jpeg)
そんな彼が、どんな食生活をしていたのか。
意外にも、このテーマには多くの興味深いヒントが残されています。
命への敬意や、好奇心あふれる観察力、そして冷静な観察眼。
彼の食への向き合い方を知ると、「人としてのレオナルド・ダ・ヴィンチ」がぐっと身近に感じられるかもしれません。
レオナルドはベジタリアンだったのか?
ダ・ヴィンチが菜食主義者だったかどうかは、実は今も議論が続いているテーマです。
彼が菜食主義だったかどうかは不明ですが、彼の手稿には、動物の命を尊重する記述がいくつも見られます。
たとえば、「動物たちは人間の手によって殺され、その死体は人間の墓場(=胃)となる」という一節(※『Codex Atlanticus:アトランティコ手稿』 より)は、肉食に対する皮肉とも受け取れます。
また有名な逸話として、市場で売られていた鳥かごの鳥たちを買い、逃がしてやったという話が初期伝記に残っているんだとか。
事実かどうかは不明ですが、彼の“命を慈しむ”姿勢を象徴するエピソードとして語られています。
%20(1).jpeg)
さらに、師であり親友でもあった彫刻家ヴェロッキオのアトリエでは、肉体を描くために生きた動物を観察する機会が多かったと言われています。
そうした環境で、彼が動物の苦しみに心を寄せたとしても不思議ではありません。
彼にとっては、「食」も科学であり芸術だった
.jpeg)
ダ・ヴィンチはただのグルメではありません。
食そのものを「人体のしくみ」や「自然の法則」と同じように探究の対象として見つめていました。
彼のノートには、消化のプロセスや食材の組み合わせに関するスケッチ、健康管理への言及もあります。
中には「夜に重いものを食べない方が良い」といった、現代にも通じるような健康志向のメモも。
特筆すべきは、『Codex Atlanticus(アトランティコ手稿)』に記されている、食に関する“機械”のスケッチ。
自動でパスタをこねる装置や、ワインを冷やす仕組み、厨房の効率化を狙った調理道具の改良図など、現存する手稿に描かれたアイデアはどれもユニークです。
彼にとって「料理」もまた、芸術であり、科学であり、実験の場だったのでしょう。
名画に映る、質素と感情の食文化
彼の代表作、『最後の晩餐』(1495–1498)。
キリストが弟子たちと食卓を囲む場面を描いた壁画は、誰もが一度は見たことがあるのではないでしょうか?
.jpeg?w=600&h=420)
そんな有名すぎる壁画ですが、卓上に注目したことはありますか?
そこに登場するのはパン、ワイン、そしてわずかな果物や魚といったシンプルな食材。
これは聖書の記述に基づく構成ですが、彼自身が贅沢を避け、質素な食事を重んじたという人物像と重なるようにも見えます。
さらに注目したいのは、食卓を舞台に繰り広げられる人間ドラマ。
イエスの「裏切り者がいる」という言葉に弟子たちが動揺するその一瞬を、レオナルドは見事に切り取りました。
食卓は、単に栄養を摂る場ではなく、人間性や感情が交差する場所。
そう考えていた彼の人間観察力が、この作品には濃密に込められているんです。
レオナルドが見つめた、食へのまなざし
.jpg)
レオナルド・ダ・ヴィンチの食への姿勢には、今の私たちにも通じるメッセージがあります。
それは、「食事は、ただ食べるだけではない」という視点です。
大量生産・大量消費が当たり前になった現代だからこそ、一つの食材がどこから来て、どんな命の循環の中にあるのかを想像する。
どんな機械で何がつくられ、体内でどのように循環していくのかをイメージしてみる。
その食卓では、誰が何を考えているのか、思惑を観察してみる。
そんな目線を持つだけで、日々の食卓の意味が少し変わって見える気がしませんか?
