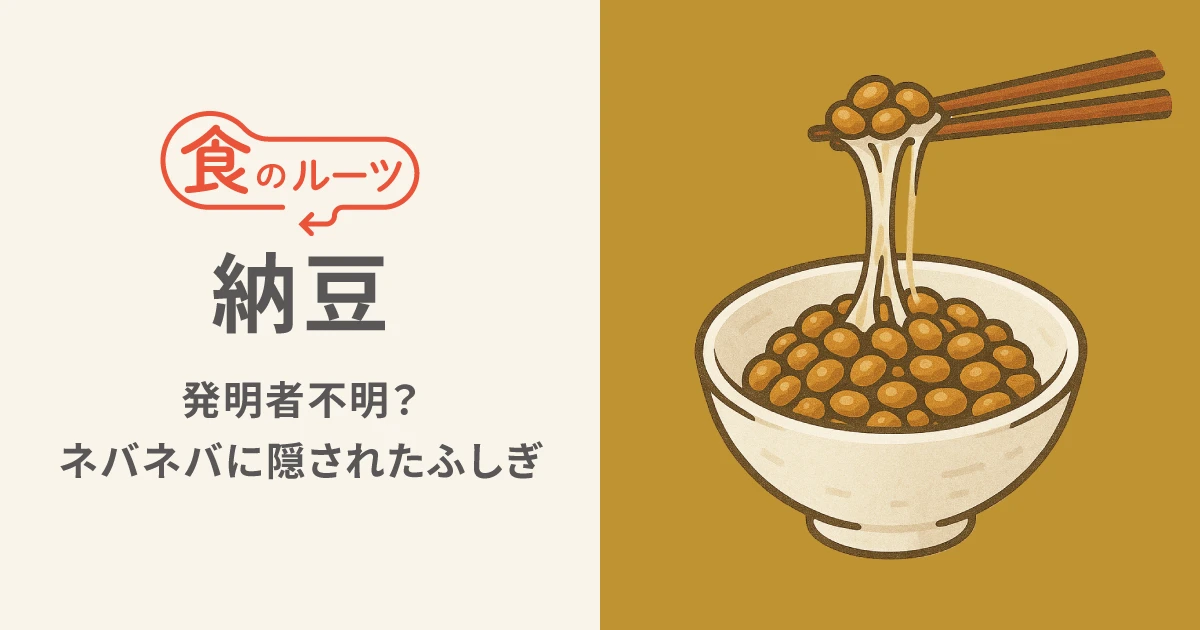
発明者不明?ネバネバに隠された納豆のふしぎ
食のこと
朝の食卓で、白いごはんにとろ〜りとかけて食べる納豆。
日本の定番食品としてすっかりおなじみの存在ですが、「納豆って、そもそもいつ、どこで、どうやって生まれたの?」と疑問に思ったことはありませんか?
.jpeg)
ネバネバと糸を引く独特の見た目や、クセになるような香り。好き嫌いが分かれるとはいえ、日本の食文化に深く根づいている納豆には、じつははっきりとした“はじまり”がないのです。
今回はそんなミステリアスな納豆のルーツを、発酵食品としての視点から紐解いてみましょう。
たまたま?それとも必然?「偶然発酵説」
納豆の起源として最も有力とされているのが、「偶然できた」という説です。
これは、炊いた大豆をワラで包んで持ち運んだり保存したりした際、稲ワラに付着していた納豆菌(枯草菌の一種)が働いて自然発酵し、納豆ができあがったという考え方です。
納豆菌がもっとも活発に働くのは40℃前後。
高温多湿の日本の気候と、稲作文化の中で手に入れやすいワラ。
この2つの要素が偶然組み合わさり、大豆がネバネバと糸を引く食品へと変化した…そんな“発酵の奇跡”が、納豆のはじまりだったのかもしれません。
.jpeg)
この説を裏づけるかのように、「○○の殿様が戦の途中で偶然納豆を作った」などの伝承が日本各地に残っています。
有名なのは、平安時代の武将・源義家が東北遠征の際に、炊いた大豆をワラに包んでおいたところ発酵してしまい、それを食べたらおいしかった──という話。
そのまま「納めた豆」、つまり“納豆”と呼ばれるようになった…という語源説も語られています。
もっとも、これらはあくまで伝承であり、歴史的に裏づけられた記録があるわけではありません。
ですが、発酵が“偶然の産物”だったという考え方は、味噌やワイン、チーズなど他の発酵食品にも共通しています。
納豆もまた、人と微生物との思いがけない出会いから生まれた、奥深い食文化のひとつなのですね。
世界にもあった!「納豆そっくり発酵食品」
納豆=日本の食べ物、というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実は似たような発酵大豆食品は、アジア各地に存在しています。
たとえば、ネパールやインド北東部の「キネマ」、ミャンマーの「ペーポゥ」、タイの「トゥアナオ」などは、どれも納豆と同じく枯草菌の仲間によって発酵させる食品。
強い香りと、粘りを持つものもあります。
また、インドネシアで親しまれている「テンペ」も、発酵大豆食品として有名です。
こちらはテンペ菌(リゾプス菌)というカビの一種で発酵させるため、ネバネバはなく、ブロック状にしっかりと固まっているのが特徴です。
▼インドネシアで親しまれている「テンペ」

このように、発酵に使う微生物こそ異なるものの「大豆×高温多湿×菌」という条件がそろえば、自然と似たような食品が生まれる。
そんな共通点が見えてきますね。
つまり納豆は、“日本が唯一発明した食品”というよりも、“日本の気候と文化の中で根づいた発酵食品のひとつ”と言えますね。
だからこそ、東北から九州まで、各地に多様な「ご当地納豆」が存在しているのかもしれません。
ワラからパックへ。進化を続ける納豆文化
.jpeg)
かつてはワラで包んで販売されていた納豆ですが、戦後の衛生環境の改善と流通の発展により、1970年代後半ごろから発泡スチロール容器に入った「パック納豆」が一般的に。
冷蔵保存が可能になったことで、納豆は全国どこでも手軽に手に入る食品となりました。
さらに近年では「ひきわり納豆」「黒豆納豆」「におい控えめ納豆」などのバリエーションも増え、スーパーの棚をにぎわせています。
海外では「スーパーフード」として紹介されることもあり、ヴィーガンや健康志向の人々から注目されています。
偶然から生まれたこのネバネバ食品が、いまや日本を超えて世界の食卓へと広がろうとしている…ちょっと感慨深いですね!
